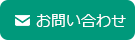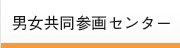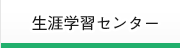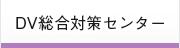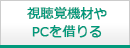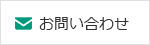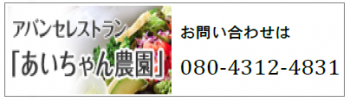アバンセ館長コラム第37号(令和7年5月)
「“お米”にまつわるアラカルト 4題」
【お米の価格推移】
4月以降、スーパーマーケットに行くと必ずお米の価格と産地と品揃えを確かめるようになりました。5キロ入りの袋で税込み4500円を超えるのは珍しくなく、国産米以外も流通しています。10キロ入りの袋は見当たりません。この値段で10キロのお米が買えていたのはいつだったのかなと思って調べてみました。
農林水産省HPの資料では、令和2年の消費者物価指数を100としたとき、令和7年3月の時点で、パンは、125.6 、麺類は 121.9ですが、⽶類は195.3です。この数年は全般的に物価高で、とりわけお米は2倍近い上昇率。過去にない急カーブです。5年前には4500円でお米10キロが買えていました。
お米の価格高騰の理由は複合的といわれています。猛暑による収穫量の減少、コロナ禍以降の外食需要回復、訪日外国人観光客増による需要増加、中間買い取り業者の買取競争の激化などが喫緊の理由ですが、減反政策の影響、農家の担い手不足と高齢化など長期的な課題も影を落としています。
世界中でも稲作文化の発展した国、美味しいご飯が主食の国、日本。それが当たり前でした。お米の安定供給と価格引き下げは私たちの切実な願いです。
【おむすびの、むす】
3月でNHK連続テレビ小説「おむすび」の放映は終わりました。残念ながら視聴時間が確保できず内容を把握できていません。主人公の名前が米田結。ドラマのテーマも、「結ぶ」という言葉に象徴されていたようです。
最近、私が初めて知ったのは、「むす」という音韻のこと。君が代の歌詞「苔の生(む)すまで」という意味とのつながりでした。一説によると、苔が生すまでの、長い永い時間、命が生まれ、栄え、続いていくことから、むす+子=息子(むすこ)、むす+娘=娘(むすめ)という言葉になったとか。「結ぶ」とは、辞書で引くと、ひもなど細長いものを組んでつなぐ意味とも記されています。映画「君の名は」の組みひものシーンも頭に浮かんできました。「むす」という響きの奥深さ。白いご飯のお結びから、悠久の時に繰り返される生と死と命のつながりまで想像してしまいました。
【アメリカは、なぜ『米国』と書くの?】
と、子どもたちに訊かれ還暦過ぎているのに説明できず恥ずかしくなりました。改めてアメリカを米国と書く理由も調べてみました。
アメリカを漢字で表す際に使われた「亜米利加」という当て字のうち、1番目の「亜」は、亜細亜(アジア)等、他にも使うので避けられ、2番目の「米」が採用され、後に「米国」と略されて使われるようになったという説が主流です。
他の説としては、日本が鎖国を終えた後、西洋の学問や文化を中国経由で取り入れることが多く、中国の音訳方法を参考にしていました。中国語の発音「米(mī)」は、英語の「America」の発音に似ており、これが漢字表記に影響を与えた可能性があるという説もあります。アメリカ人を指す言葉として使われていた「メリケン」は、英語の「American」を聞き間違えて生まれた言葉で、この「メリケン(漢字表記は、米利堅)」という言葉も、アメリカを「米」で表記する背景にあるとされています。
【米寿~漢字の面白さ】
漢字は興味深いですね。最後に米寿を取り上げてみます。米という漢字を分解して、八十八という数字の意味に用い、数え年(最近は満年齢でも)88歳の長寿のお祝いをします。それが米寿です。テーマカラーは、黄色や金茶色だそうです。ちなみに、77歳のお祝いは喜寿。「喜」の旧字体「㐂」が「七十七」に見えるからで、テーマカラーは紫です。99歳のお祝いは、白寿。これも「百」という漢字から「一」歳引き算したら、「白」の文字になるという頓智みたいな命名です。テーマカラーは、もちろん白。いやはや…なかなか面白いですね。

アバンセ館長 田口香津子 プロフィール
アバンセ館長
佐賀女子短期大学 学長 (2018.4-2022.3)
認定NPO法人 被害者支援ネットワーク佐賀VOISS理事長