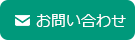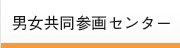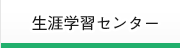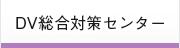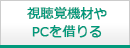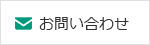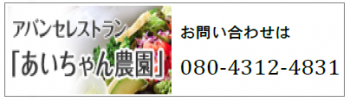アバンセ館長コラム第26号(令和6年5月)
アバンセ館長コラム第26号 「したたか」とは、「強か」と書く ~「虎に翼」の面白さ~
「強」という漢字には「つよ(い)」以外にもいくつかの読み方があります。
「強(し)いる=無理にさせるの意」「強(こわ)い=硬いの意」「強(あなが)ち=必ずしもの意」でも使われますが、したたかという言葉にも使われるのですね。
4月に始まったNHK朝ドラ「虎に翼」の主人公猪爪寅子(演じているのは俳優の伊藤 沙莉さん)のモデルは、日本で最初の弁護士、そして戦後には裁判官になった方だそうです。
寅子は「はて?」と、疑問や義憤を感じることに黙っていられない率直さを持っているが故、周囲と衝突する場面がいくつか描かれています。その寅子に対して、親友の花江が、どうしても欲しいものがあるなら、したたかに生きることを諭します。
その場面を見て、私自身の過去に思い至りました。
私も、正しいと思うこと、間違っていると思うことを懸命に訴えて、相手の無関心や無理解にぶち当たり、悔しがった若い日があります。一歩引いて我慢をした先に得るものもあるのよというメッセージを若い頃は呑み込めませんでした。しかし、様々な経験を経て、自分が目指すことを実現させるためには、相手の立場に一度立ってみて、その一枚上手をいき、相手からの協力を引き出す戦略を持つことが必要だとじわじわ学んでいきました。
それを花江さんから、「したたかに生きる」という言葉で表現してもらった気になりました。直線はポキッと折れやすい、曲線はしなやかでかえって折れにくいと言います。でも、まっすぐな主張が世の中を動かすこともあります。どっちがいいかではなく、どっちもありなのでしょうね。
この朝ドラ「虎に翼」の脚本家は、新進気鋭の吉田恵里香さん。
「恋せぬふたり」で向田邦子賞を受賞されています。朝ドラの舞台は、昭和初期、第二次世界大戦前の日本。当時の男尊女卑の風潮が、いろいろな場面で描かれています。しかし、脚本家の吉田さんが、主人公だけでなく、登場人物それぞれのキャラクターを通して構築している世界は、単純な対立の構図に終わっていません。私たちが無意識に抱くステレオタイプのものの見方を揺るがし、『人と人とが真に出逢うことで芽生える希望』を感じさせる展開が待っています。
たとえば、こんなシーンがありました。
家庭内では有能ながら、世間には男性を立てすんっと振る舞う母は、娘の幸せは結婚と言いきります。母の有能さを知り、両親が幸せに暮らしていると分かっていても、それでも結婚は女性には地獄に思えると口走る娘は、どうしたら母を説得できるかを偶然再会した法律家に尋ねます。やりとりするうちに、女が法律を学ぶとは時期尚早というような言葉が返ってきます。それを耳にして、娘以上に憤る母は、地獄を生きる娘の覚悟を確かめ、六法全書を買いに行きます。
印象深いシーンをもう一つ。
農家の二女で壮絶な苦労をしながら法律を学ぶ山田よねが、みんな弱音を吐かずに頑張っていると花江に怒りの言葉をぶつけます。すると、寅子が、弱音を吐いてもいい、受け止めることはできるのでは、と率直につぶやきます。まわりの友人たちも、はっとして、弱音を吐こうと口にします。そして帰り際、よねにも、今のまんまの(嫌な感じの)よねさんでいいという旨を伝えます。
もちろん男女もそうですが、それ以外にも、優劣や力の格差にあふれているのが現実の世界です。しかし、この物語には、どっちが強いとか、悪いとか、優れているとか、勝ちとか負けとかで、人と人とを分断しないメッセージが随所に散りばめられています。それぞれの己の事情を抱えている人が、相容れぬものもありながら、互いの違いから学び合い、成長していく多様性の物語だと気づかされます。それらの豊かな関係性を俯瞰できる視聴者は、今を生きる自分自身の「はて?」にも光が当たっていることを感じるのでしょう。
エンパワメントされる朝ドラです。
なんとも、したたかで面白い!

アバンセ館長 田口香津子 プロフィール
アバンセ館長
佐賀女子短期大学 学長 (2018.4-2022.3)
認定NPO法人 被害者支援ネットワーク佐賀VOISS理事長