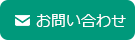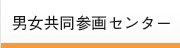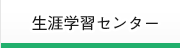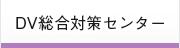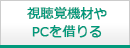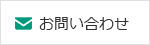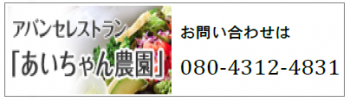令和6年度 生涯学習関係職員実践講座(基礎編2)報告
佐賀県立生涯学習センターでは、生涯学習・社会教育関係職員を対象に、必要な知識や実践力を身につける「生涯学習関係職員実践講座」を行っています。今年度は『学び直しと意識のアップデート』のテーマのもと、年間で全6回(基礎編、ステップアップ編、地域支援編 各2回)の講座を実施します。
基礎編2「未来につながる地域づくりと公民館 \今こそ公民館のハナシをしよう/」を1月29日(水)に開催しました。
チラシはこちら (613KB; PDFファイル)
未来につながる地域づくりと公民館 \今こそ公民館のハナシをしよう/
令和7年 1月29日(水) 13時30分~16時30分
東海大学総合教育センター准教授の池谷美衣子さんを講師にお招きし、地域のより良い未来につながる社会教育や公民館の取組みに必要な視点について学び、住民の暮らしに寄り添いながらできることを考えていきました。
1.公民館のチカラを見つめ直す ~社会・地域を知ることから~
【講師】池谷 美衣子 さん(東海大学総合教育センター 准教授)
はじめに池谷さんは、ご自身が公民館で仕事をした経験の中で「公民館は誰にでも開かれている場所と言われながらも、結果的に利用者(つながる相手)を選んでいるのでは」という問題意識を抱くきっかけになった出来事を紹介されました。「公民館とつながりづくり、地域づくりという明るいスローガンを聞く度にその事を思い出し、ずっと心の中にあるテーマとなっている」と打ち明けられ、「今日は皆さんが普段感じていることを素直に話せる場にしていきましょう」と呼びかけられました。
そして、自己紹介を兼ねて、この1年間仕事をしてきた中で気になっていることや悩んでいることについてグループトークを行いました。それぞれが自身の仕事をふり返りながら課題を見つめることで、今日考えていきたいことって何だろう?という意識が高まっている様子が伺えました。
公民館のチカラとは? 社会教育の基礎理解
講義ではまず「公民館のチカラ」とは一体何か?ということを共有するために、そもそもの「社会教育」について、学校教育と比較しての特徴をあげて説明されました。そして、ユネスコの『学習権宣言』に基づきながら、社会教育にとっての「学習」とは「人間を主体に変える(意思や行動によって自らの歴史/未来をつくる)もの」であると説かれました。受講者は「学習」の意義深さを知るとともに、様々なレベルでそのような学びの実践がなされている場が公民館であることに理解を深めました。
また、職員として期待されるのは「社会教育の現場で実践を“発見”し、“意味づける”こと」と「住民の潜在的ニーズを掘り起こし、社会教育の学習機会やつながりを“つくり出す”こと」と述べられ、人々の学習を下支えする役割があることを再認識しました。
社会・地域の ”変化” を知る
次に、社会教育、公民館の実践の方向性とともに押さえておくべき”地域や社会の変化”について、3つの観点から話されました。
まず、コロナ禍での経験から公民館は施設の外へ視野が広がり、それまで見過ごされてきた”公民館に来ない/来られない人たち”も公民館の対象であるという気づきがあったそうです。「どんな人でも、その人の生活や人生の豊かさを支えること」が公民館の役割として再発見され、それをどのように事業や活動につなげていくのかが、ポストコロナ社会の公民館を考える上での大きな課題だと述べられました。
また、人間関係の変化という点において、地縁や血縁による共同体的関係ではなく、個人の感情でつながる”選択的関係”を望む住民が主流化している中で、個人のつながる自由を尊重しつつ、地域との関わりができる関係の在り方を考えること、さらに、今後も続く人口減少社会においては、既存の組織ややり方を変えることで社会を成り立たせていく可能性を、日本以外の国から学ぶ必要もあることを指摘されました。
そして、このような社会において社会教育ができることは「地域に今いる人たちがどうやって豊かで幸福に暮らしていけるのか?それが実現できる地域とは?という視点で考え、取り組んでいくこと」だと述べられました。また、地域が変わるには、課題を抱える当事者だけではなく、地域の中での決定権や影響力をもつ人たちが学ぶことが重要であり、そのような人たちの学びのきっかけや変容を促すような関わり方がいかにできるのかを考えてほしいと呼びかけられました。
実践に学ぶ 仕事のヒントを求めて
これまでの話をふまえて、地域の中でいろいろな出会いを仕掛けたり、人の人生を支えるために取り組んだり、地域を変えるチャレンジを続けている事例として、全国各地から10個の実践を紹介されました。公民館職員のアイデアと熱意が反映されたものから、個性的で実験的な取組みをしているNPOの活動まで、様々なアクションの形を知ることができました。
池谷さんはまとめとして「社会教育には“時間軸の自由さ”という強みと、いろいろなことにチャレンジできる可能性がある。何が正解なのか分かりにくい中でも活動し続けること、視野を広げることで見つかるアイデアや次の一歩から、自分たちの取組みの意義が見出されるはずです」と、受講者それぞれの活動へエールを込めて伝えられました。
俯瞰的な視座と具体的なエピソードを交えて話される内容から、受講者は自らの仕事を考える上での現状理解と、課題に向き合うためのヒントをつかめた様子でした。
2.公民館のハナシをしよう ~今、おもうこと 私たちの仕事・公民館・地域の未来に向けて~
後半はグループで、紹介された実践の中で各自が一番気になった事例について共有した後、テーマに沿って語り合うワークを行いました。
まず、それぞれが感じている公民館の「強み/魅力・弱み/課題」を出し合い、その上で「その魅力を強めるために、また課題を乗り越えるためにどんなことができるだろうか?」という視点で意見を交わし合いました。
どのグループも、お互いに共感しながら話が深まっていき、受講者からは「他の公民館の方との意見交換はいい刺激になった」「元気や勇気をもらえた。いろいろなアイデアも出てきて、心強く感じた」などの感想が聞かれました。
『私の宣言!』発表
最後は、これから職員としてどんな力をつけたいか、また、頑張ってみたいことや意識して取り組んでいきたいことを『私の宣言!』として書き出して、一人ずつの発表タイム。「企画力を身につけて、魅力ある公民館を全力発信!」「他館のサークル見学など他の公民館を巡るツアーをしたい」「新しいことに挑戦!まずは行動してやってみる」など、それぞれの決意が込められた宣言に、全員で拍手を送り合いました。
皆さんの宣言を聞いて池谷さんは「『公民館でまだまだできることはある』という希望と確信をぜひ持ち帰ってほしい」「自分の公民館や自治体の枠を越えた仲間をつくりながら取り組んでみること。そのつながりがきっと皆さんの仕事の支えになります」「今ではSNSでいろいろな公民館の情報が得られて、こちらから発信もできる。難しいとためらわずに活用してみてください」と3つのポイントをあげて、受講者にあたたかいメッセージを送られました。
参加者の声(アンケートより一部抜粋)
- 社会教育についての理解が深まった。ユネスコの「学習権宣言」が印象に残りました。
- 講義を聞きながら、自分の中に勝手に作っていたバリアが下がっていく気持ちになり、公民館活動の可能性の広がりを感じました。
- グループワークがよかった。公民館の基本、地域づくりへの思いをもう一度再確認することができた。
- 動かないと何も変わらない。小さいことからチャレンジして少しずつ進めていきたい。
- 自分で宣言することで何ができるか考える時間になった。やる気がアップしました!