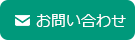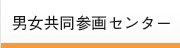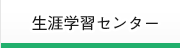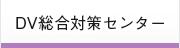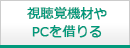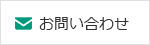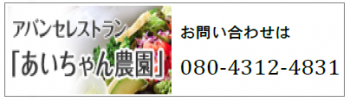令和6年度 生涯学習関係職員実践講座(基礎編1)報告
佐賀県立生涯学習センターでは、生涯学習・社会教育関係職員を対象に、必要な知識や実践力を身につける「生涯学習関係職員実践講座」を行っています。
今年度は『学び直しと意識のアップデート』のテーマのもと、年間で全6回(基礎編、ステップアップ編、地域支援編 各2回)の講座を実施します。
基礎編1は、7月2日(火)に小城市牛津公民館にて開催しました。(共催:小城市教育委員会)
基礎編1「聞いてみよう!『社会教育・生涯学習』の基本と疑問」チラシはこちら (741KB; PDFファイル)
聞いてみよう!「社会教育・生涯学習」の基本と疑問
令和6年 7月2日(火) 13時30分~16時30分
第1回目となるこの講座では、講師に上野景三さん(西九州大学 副学長)をお招きし「社会教育」や「生涯学習」の理念等の基本から学ぶとともに、担当職員としての仕事の心構え等について、講義や受講者同士の語り合いなどを通して考えていきました。
1.社会教育・生涯学習の基本をまなぶ ~職員としての仕事と役割を知ろう~
【講師】上野景三 さん(西九州大学 副学長)
今回は、市町の担当課や公民館などの職員となって1年目という受講者が大半ということもあり、「社会教育」と「生涯学習」の言葉の説明から始まりました。
「社会教育」は元来、❝自治的な『社会』をつくる❞という大きなテーマがあった中で、その社会を担う『人』を育てるという観点が位置付けられている一方、「生涯学習」は一人の人間『個人』が前提にあり、その生涯をどのように充実させていくのかという観点がベースとしてあります。
上野さんは「社会をつくっていく時に、一人ひとりの人間の成長や発達というものがなければ、豊かな社会にもつながらない」と述べられ、「社会教育」「生涯学習」それぞれを大事に捉える必要性を学びました。
そして、社会教育・生涯学習をめぐる歴史的な展開や法制度的な変遷、諸外国との比較について具体的な事柄も交えながらお話しいただき、受講者は、国の文化や特色が反映されながら発展してきたことに理解を深めました。
最後に、社会的な課題に対して国のコミュニティ政策が力を入れて取り組まれている中で、地域(公民館)で様々な事業や取組みをしようと勧められる現在の情勢に「社会教育や公民館への期待がある」と指摘された上で、公民館としての軸足を持ちながら仕事をしていくのが大切だと伝えられました。
先輩トーク&インタビューダイアローグ
続いて、社会教育行政や公民館現場で長年仕事をされてきた3名の先輩ゲストに、この仕事に携わるようになったいきさつや、経験から感じる仕事の面白さ、やりがいについてお話しいただきました。
▲大橋隆司さん ▲岩本未央子さん ▲田中みさ子さん
大橋隆司 さん(パレットクラブ牛津 幹事)
元々は文化財担当職員として牛津町教育委員会に入り、地域の運動会や文化祭の手伝いをしているうちに、正式に公民館に配属された大橋さん。当時、学校の週5日制が完全実施されることに伴い、子どもたちの放課後の居場所づくりが大きな課題であり、地域での体験活動プログラムの立ち上げに奔走したことを紹介されました。指導者やボランティアを集めるためにイベントに来た保護者に声をかけたり高校に相談するなど、知恵を出して苦労しながらも、協力してくれた地域の大人や高校生たちが子どもたちと仲良くなり「ここでしかできない冒険的な体験活動を実現できたことが思い出深い」と語られました。
岩本未央子 さん(唐津市肥前公民館 館長)
前職は小学校の教諭として30年以上、学校現場で子どもたちと関わりながら仕事をされてきた岩本さん。退職後に声をかけられ、公民館の館長として仕事を始めた頃は、地域とのつながりも少なく不安が大きかったそうです。それでも「人と関わることが好き」「話をじっくり聞ける」という自身の強みをいかして「日々、積極的に来館者と接することで、関係性を広げることができた」と話されました。また、幅広い年代の来館者と接する中で自分自身の学びになることが多く、公民館が楽しい場所だと実感できたことが、この仕事を続けられている理由の一つと語られました。
田中みさ子 さん(佐賀市立春日北公民館 職員)
地元校区の公民館職員としてスタートしてから、現在は4館目となる公民館に勤められている田中さん。「悩みながらも、楽しいと思えることが多い」と、コロナ禍に試行錯誤しながら実施したオンライン交流会や公民館でのお茶の間的な集いの場づくりなどを紹介されました。大事にしているのは「話を聞くこと。聞いたことを書いて見える化、共有すること」。そうすると後から他の人たちも話題に加われて、次の展開につながっていくと身をもって感じているそうです。また「自分が動いてすべてをするというよりも『誰かが何かをできるステージ』をつくっておく」ということを意識していると話されました。
インタビューダイアローグ
上野さんが聞き手となって「つながり」をキーワードに3人の話を深ぼり、地域の人や団体、学校、そして公民館同士がつながったエピソードの数々から、そのアプローチの仕方を詳しく聞くことができました。上野さんは「公民館と地域のつながりを考える時、『今、つながっていないところ、つながりが求められているところはどこだろう?』という視点を持つことが大事」と述べられ、3人の話から様々なつながりのあり様を考える時間となりました。
2.現場の声からまなびあう ~疑問をそれぞれのチャレンジに!~
後半は、グループで自己紹介を行った後、受講者自身の仕事上の疑問や悩みをグループメンバーと聞きあうワークを行いました。
「講座のつくり方や参加者の集め方」「公民館でやりたいことと目的について」「若者と公民館のつながりをつくるための方法やアイデア」「職員としての働き方や仕事内容について」などの話題があがっており、先輩ゲストも加わってアドバイスしあったり、意見を出して一緒に考えを深めながら、共感しあう姿が見られました。
質問タイム
前半のトーク内容も含めて、先輩ゲストへ『来館された方と話し続けるコツは?』『地域の人と仲良くなる方法は?』などの質問がありました。「まずは自分のことを話して、小さいことでも情報発信していく」「相手に関心をもって接する」「困りごとを話して、お願いできる人に頼ってみる」「仲良くなった人から、仲間のネットワークを広げる」など、それぞれの経験からヒントとなることを答えていただきました。
チャレンジ宣言
最後に、講座を受けての気づきや学んだことから、これからチャレンジしていきたいこと、頑張って続けていこうと決意したことを『わたしのチャレンジ』として書き出し、見せ合いました。「名前を覚えて、話ができるきっかけをつくる」「来館者ともっと身近に、もっと仲良くなる」「地域の人に頼る」「自分もわくわくする講座を開催できるように頑張りたい」など、今後に向けた思いを共有することができました。
上野さんはまとめとして「公民館はこういうものという正解や定番があるわけではない。施設の名称も『公民館』だけではなく、それぞれの呼び方がある。共通しているのは、そこを利用しやすくしたり、参加しやすくしたり、つながりをつくったりするために、いろいろなひと工夫ができるということ。この仕事の面白さはそういうところにある。『定番は自分たちでつくっていけるもの』と楽しむような気持ちをもって、チャレンジしてみましょう」とエールを送られました。
参加者の声(アンケートより一部抜粋)
- この仕事に就いて一年目で模索状態でしたが、社会教育の理念やその活動について知れた良い機会になった。
- 先輩方の経験談を聞き、他の市町の職員の方とも話ができて刺激になった。
- 自分が一番に疑問に思っていたことに対して、他の人の意見を聞けてすごくためになった。ここで学んだことをいかして頑張っていきたい。
- 来館者ともっと仲良くなって、よりよい公民館にしていきたいです。
- 明日からまた、人とのご縁を楽しみながら頑張ります。