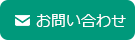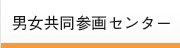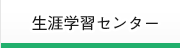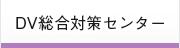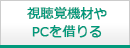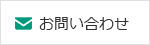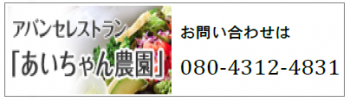令和6年度 家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修) 第4回報告
多様化する社会で大切にしたい親子への支援
リーダー研修は、家庭教育・子育て支援に関わる活動経験年数が3年以上の方を対象とした連続5回講座です。
今年も県内各地の様々なフィールドで家庭教育や子育て支援の活動をされている皆さんが集まりました。
今年の講座では、少し視点を広げて『多様化する社会』をキーワードに、今まであまり取り上げてこなかった『ジェンダー』『父親支援』などもテーマにしています。
様々な経験を重ねてきた支援者の皆さんと「多様化する社会で大切にしたい親子への支援」について、一緒に考えていきました。
R6家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修)チラシ (811KB; PDFファイル)
第4回 佐賀県の「父親支援」のこれから ~トーク&交流会~
【開催日時】令和7年1月9日(木)13時00分~15時00分
【トークゲスト】
小﨑 恭弘さん(大阪教育大学教授/元附属小学校長)、黒木 由美さん(元佐賀市子育て支援センター所長)
中村 充朗さん(いまパパ.共同代表)、中與 真也さん(佐賀市立若葉保育所保育士)
【コーディネーター】
山口 ひろみさん(NPO法人唐津市子育て支援情報センターセンター長)
トーク 佐賀県の「父親支援」のこれから
第3・4回は同日開催の「公開講座」ということで、多くの方にご参加いただきました。
午後(第4回)は、午前中の講義に引き続き小﨑さんと、県内から3名のトークゲストをお迎えし、それぞれの活動や父親の立場から感じていること、また「佐賀県の父親支援のこれから」についてお話いただきました。
コーディネーターは山口ひろみさん(唐津市子育て支援センターセンター長)です。
黒木由美さんは、平成19年に設立された佐賀市子育て支援センター「ゆめぽけっと」の初代所長を務めていらっしゃいました。ゆめぽけっとは当時、土日も19時まで利用ができ、土日はパパたちの利用も多かったそうです。利用するママたちは、自然にお話をしたり交流が生まれるそうですが、パパたちはそれが中々難しい様子。黒木さんは、自然な感じでパパたちに声をかけたり、気の合いそうなパパ同志を繋いだりし、交流を促していたそうです。
また、「サガンパパサロン」を定期的に開催し、パパたちも親睦を深め、「パパレンジャー」などのチームもでき、イベントなどで活躍されたそうです。敷居を低く、どなたでも参加しやすい環境や雰囲気作りが大切と話され、黒木さん自身がパパたちとお話しするのが大好きだったと楽しそうに当時を振り返りました。
小﨑さんは、「まさに仲人役ですね」とおっしゃられ、保育と子育て支援は似てるところがいっぱいあるけれど、一番違うのは「つなぐ機能」。子育て支援は、黒木さんの仲人力のような「つなぐ機能」がとても大事だと話されました。
中村充朗さんは、ご自身のお子さんが低出生体重児で生まれた際に「自分が守らなければ」と初めて父親の自覚をし、それから子どもに関するニュースが気になり始め、児童虐待で命を落とす子どもが多いことにショックを受けたそうです。その背景を調べ、父親の家庭における関わりで防げる部分があるのではと考え、パパたちが子どもと一緒に楽しみながら過ごせるサークルを作りたいと思ったそうです。
Facebookで呼びかけると運良く一人のパパが反応してくれ、二人で2016年に「いまパパ.」を立ち上げます。そして、地元伊万里の子育て支援センターに来ているパパたちにも声をかけ、1回目のイベントでは8名がメンバーになりたいと集まり、活動がスタートしました。「いまパパ.」のイベントでは、必ずパパと子どもが一緒に参加。その時間はお母さんの自由時間にもなっているそうです。
父子キャンプや、家族みんなで作る手形アートなど様々なイベントを開催してきたそうですが、一番盛り上がったのは「段ボールハウスづくり」。みんな(参加者と主催者)で一緒に何かを作りあげることで、その後のパパたちの横のつながりが持てたと話されました。
小﨑さんは「パパ向けのイベントは、男性に近いキーワード『段ボール、釣り、キャンプなど』でプログラムすると集客しやすい。まずは、入口としてパパたちに子どもと遊ぶ楽しさを実感してもらい、そこから連続講座などで父親同士が主体的に交流、活動していくような仕掛けが効果的」とアドバイスされました。
中與真也さんは、佐賀市の公立保育所に勤務して12年目。男性の保育士はまだ2名ということです。保育所でのエピソードとして、年長児を担当の年、保護者役員を募集する時にパパたちにたくさん声をかけ、役員になってもらった年は、パパたちの行事への参加率が大きく伸びたことなどを紹介してくれました。
家庭では、2児の子をもつ父親として、同職の妻、家族の協力を得ながら仕事と子育ての両立に奮闘されています。ですが、子どもが病気で休みをとらなければならない時に、自分も休みを取れなくはないけれど、心のどこかで世間体を気にしてしまい、妻に休みを取ってもらうことが多くてもどかしい心境も話してくださいました。
小﨑さんも、昔同じような境遇(妻も保育士)の保育士さんで、男性の保育士の研究もされており、まだまだ保育士をはじめ子育て支援センターなど、子育てに関わる職場に男性が少ない現状を話されました。その中で「当事者支援」という考え方「当事者のことは当事者が分かって決める」を紹介され、もっと子育ての現場に男性が増えていけば、いろんなことが変わっていくと話されました。
コーディネーター山口ひろみさん&トークゲスト小﨑恭弘さん
交流会 トークフォークダンス
後半は受講者、ゲストも全員参加のトークフォークダンスです。今回の講座で何度も出てきた「つながり」を広げようということで、二重円になり1組1分で自己紹介と「父親支援のこれから」について語り合いました。
終了後、コーディネーターの山口さんから「小﨑さんをはじめ、皆さんからお話しがあったように、父親支援はこの『つながり』が一番大事だと思います。今日出会ったみなさんとの『つながり』を今後の活動に活かしていただき、佐賀県の父親支援が盛り上がっていけばと思います」とおっしゃいました。
最後に小崎さんから「佐賀は熱い!いろいろな想いをもった皆さんの初めの一歩が、佐賀のパパ、子ども、ママ、家族を幸せにする一歩につながっていくと思います。一緒に頑張りましょう!」とエールをいただきました。
会場が盛り上がったところで、記念撮影をして終了しました。たくさんの方のご参加ありがとうございました!
お知らせ「父親支援マニュアル」
小﨑さんがメンバーを務める「父親の子育て支援研究班」が作成した「父親支援マニュアル」が、
国立成育医療研究センター・研究所のHPで公開されています。
父親支援が多くの自治体・地域に広まることを目指して作成されています。是非ご活用ください↓
https://www.ncchd.go.jp/scholar/research/section/policy/project/2024_manual.html
(令和6年度こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「父親の子育て支援推進のためのプログラム確立に向けた研究」)
受講者の感想(アンケートより抜粋)
- 父親支援に取り組む様々なゲストの皆さんのお話が聞けてよかったです。お父さん側の本音も聞けてよかったです。参加の皆様と実際にお話が出来てとてもよかったです。
- 現場や家庭でのリアルな声が聞けて良かったのと、それに対してのアンサーを小﨑先生が分かり易く教えて下さったのでこれからに生かせそうです。ありがとうございました。
- トークフォークダンスとっても良いですね。是非取り入れたいと思いました。
- いろいろな方からエネルギーをいただき、一歩踏み出し、がんばろうかなあと思い始めています。