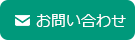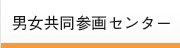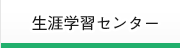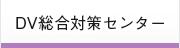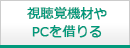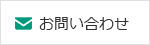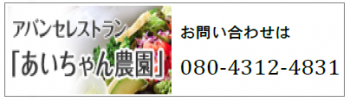令和6年度 家庭教育支援者リーダー等養成講座(支援者養成講座)第2回報告
親子への支援を考える3ステップ講座 ~多様な親子 多様な家族に 寄り添う支援をめざして~
支援者養成講座は、家庭教育・子育て支援に関わる活動が3年以内の方、また、これから活動したいと考えている方を対象とした連続3回講座です。今年度は多様化する社会で求められる視点は何だろう?と、親や子や多様な家族に寄り添う支援について考えました。
家庭教育支援者リーダー等養成講座(支援者養成講座)チラシはこちら (1498KB; PDFファイル)
第2回 親子支援の中のジェンダー ~ケースから考えてみよう~
令和6年12月13日(金)13時30分~16時30分
第2回目の講座は、親子支援の中のジェンダーを考えてみようと、福岡大学人文学部 教育・臨床心理学科 教授の藤田由美子さんをお招きしました。
講師:藤田由美子さん(福岡大学人文学部 教育・臨床心理学科 教授)
1. なぜ「ジェンダー」?
講義の前半はジェンダーについて考えることの意味について。藤田さんは始めに自身の経歴を辿りながら、男女の性別によって選択が分けられがちなランドセルの色や進路、趣味などに「なぜ?」と疑問を感じたこと、ジェンダーについて研究を始めた経緯について話されました。そして、子どもや保育の観察調査を進める中で、性差別の意図はないけれど、お絵かきの画材や発表会の曲目など、男女で分けることがしばしば「当たり前」になっている場面があることに気付いたそうです。また、それは大人だけでなく、子ども自身の発言にも見られました。似たような場面を目にした、経験したなど、頭をよぎった方もいるかもしれません。参加者のみなさん「うんうん」と頷きながら耳を傾けていました。
さらに、藤田さんはジェンダー問題が社会の中でどのように興味関心を持たれ、取り扱われてきたか、その潮流にも触れられました。最近はSDGsで取り上げられたこともあり、関心の高まりを感じている方も多いのではないでしょうか。「ジェンダー・ステレオタイプ」「アンコンシャス・バイアス」「性の多様性」「子どもの権利」のキーワードを挙げ、例を示しながらその意味を説明いただきました。「無意識のうちに身に着けている偏った考え“アイコンシャス・バイアス”。まずはその存在に気付くことが大切です」と話されました。
2.ジェンダーに配慮した親子支援のために 『保育のなかのジェンダー』に学ぶ
講義の後半はジェンダーに配慮した親子支援について、藤田さんの著書『15のケースで考えよう 保育のなかのジェンダー(チャイルド本社2023年)』から学びました。
まずは動画を視聴。子どもの名前や服装から認識される性によって、大人が用意する遊びやおもちゃ、対応が違うことがわかる動画に、はっとさせられた方も多かったようです。また「男の子なんだから泣かない」「女の子なのに理数系なの?」といった声かけにも、無意識のうちにジェンダーステレオタイプ(性に関する固定的な見方や考えなどの固定観念)が含まれています。そのような大人の声かけや評価は、子どもたちの間で共有されることも。本来関係のない性別による思い込みや決めつけについて「子どもの可能性を広げるために、男の子なんだから女の子なんだからという風な声かけをしないで、みんなが経験を豊かにできるような働きかけをする。子どもたちが自分で選べるように、いろいろなことに触れられるように、選択肢を用意することが大事じゃないかと思います」と藤田さん。
他にも、なぜ保育職は女性が多く管理職は男性が多いのか、母親に偏る家事育児の負担、そしてさまざまな家族のかたちについても触れていただきました。
講義の最後は子どもの人権や、多様な性についてです。全ての子どもが安心して生活する権利を持っていること、その子どもを独立した人格の持ち主として考えることの大切さ、そして心と身体の性が異なる子どもへの対応として子どものありのままの姿を受け止めることの大切さについて学びました。
3. グループワーク
後半はグループワークです。「子どものころのジェンダー経験」「自分がつい言ってしまった、やってしまったジェンダーステレオタイプの経験」をテーマに話し合いました。他の人の話を聞いているうちに、「そういえばこれもあった!」「これはどうなの?」「そうそう!」と、さらに沢山の意見や疑問が出てきて盛り上がる皆さん。学校、家庭、地域、職場など様々な場面にジェンダーの視点を広げて考えられている姿が見られました。
最後は「ジェンダーを意識して、親子支援で心がけたいこと」を出し合って、グループごとに発表。
皆さんの意見から、また、具体的な事例について考えることで、より学びを深めることができたのではないでしょうか。藤田さんは最後に「子どもや保護者の方、地域との関わりの中で、全ての子どもが尊重され、自分らしく生きることを保証するために、今回の学びや知識を役に立てていただければ幸いです」とエールを送られました。
参加者の声
アンケートより(一部抜粋)
-
自分自身はジェンダーについてあまり深く考えずに受け入れて生活してきました。それだけに知らず知らずのうちにジェンダーステレオタイプになっていたかも・・・。子どもを(大人も)男女関係なく一人の人格として尊重して接するということを気にとめることが大事だと学びました。
-
ジェンダーの言葉は色々な場面でよく耳にしていたけど、深く掘って考えたことがなかったので、全ての内容が腑に落ちました。特に先生の話を聞いた後にグループワークで落とし込めたのがよかったです。
-
改めてジェンダーについて考えることができて良かった。小さい頃からの周りの人や環境が大きく影響することをしっかり頭に入れた声かけや関わり、選択できる工夫をしていくことが大切だなと思った。
-
この講座がなければ具体的にジェンダーについて考えることはなかったかもです。先生の講義を聞けたことは貴重でした。
- 周りの意識を変えることは難しいと思うが、私たち支援者が意識し続けることで変われることを信じ、啓発していけたらと思う。ジェンダーの講義を初めて受講できて良かったです。良い学びをありがとうございました。
-
動画を見て、私も同じように男の子には男の子のおもちゃを渡していたと思います。今後、子どもたちに限らず、色んな価値観があるのだと思いながら人と接していきたいと思います。
-
自分が育ってきた時代と今から子供達が生きていく時代は大きく変わっていると思っています。常に学び続けることが大切だと改めて思いました。