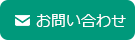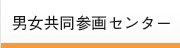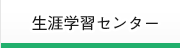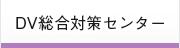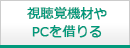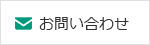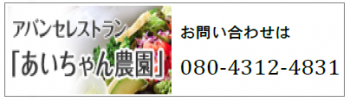令和6年度 家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修) 第3回報告
多様化する社会で大切にしたい親子への支援
リーダー研修は、家庭教育・子育て支援に関わる活動経験年数が3年以上の方を対象とした連続5回講座です。
今年も県内各地の様々なフィールドで家庭教育や子育て支援の活動をされている皆さんが集まりました。
今年の講座では、少し視点を広げて『多様化する社会』をキーワードに、今まであまり取り上げてこなかった『ジェンダー』『父親支援』などもテーマにしています。
様々な経験を重ねてきた支援者の皆さんと「多様化する社会で大切にしたい親子への支援」について、一緒に考えていきました。
R6家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修)チラシ (811KB; PDFファイル)
第3回 多様化する社会で必要な「父親支援」~はじめる・つながる・そだてる~
【開催日時】令和7年1月9日(木)10時00分~12時00分 【講師】小﨑 恭弘さん(大阪教育大学教授)
第3・4回は同日開催の「公開講座」ということで、多くの方にご参加いただきました。午前(第3回)の講義の講師は、小﨑恭弘さん(大阪教育大学教授)です。
小﨑さんは、兵庫県西宮市で公立保育所初の男性保育士で、三人のお子さんが生まれた際には、それぞれに育児休業を取得され、それらの経験をもとに「父親の育児支援」の研究をされています。また、NPO法人ファザーリング・ジャパンの顧問も務めておられ、様々な経験からユーモアを交えて「多様化する社会で必要な『父親支援』」をテーマに分かりやすく楽しくお話しいただきました。
父親の育児を取り巻く環境の変化
はじめに、近年「父親の育児」について関心や注目が高まっている背景とされる、社会の多様化についてお話しいただきました。
女性の社会進出がすすみ、共働き家庭が増えていき、現在では専業主婦家庭は共働き家庭の半分以下となり社会のスタンダードモデルとなってきました。ですが、父親の育児時間は母親と比べ約三分の一。その背景には男性の長時間労働があり、国は育児休業法を改定するなど、様々な施策に力を入れています。
そんな中、男性が仕事と育児の両立などに悩み「産後うつ」になることも報告されています。また、男性の「つわり」もあるそうで、講師の小﨑さん自身も経験したそうです。これまで女性、男性と区分されてきた領域や支援が限界にきており、見直しが必要で、人権をベースにした総合的サポート支援が必要だと話されました。
父親の育児支援を考える
これまでの子育てにおける「父親」のイメージは「二番目の親」「母親のサポート役」などとされ、「仕事」という免罪符が、父親を子育てから遠ざけてきました。このような「母親=子育て」「父親=仕事」とされる社会文化がずっと共有され続けており、男性を追い詰め(自殺など)、女性を追い詰め(育児の過度の負担、虐待など)その結果、子どもや家族を追い詰めることにもつながっているそうです。
これを解決する方法が「父親の育児」で、「父親の育児は5人を幸せにする」とおっしゃいました。
- 子ども→多様な価値観
- 母親→育児不安からの解消
- 父親→生きている意味の確認
- 企業→効率化とメンタルヘルス
- 社会→少子化対策
父親支援とは
父親支援とは「父親が親としての本来の力が発揮できるようにするため、支えていくこと」とし、
「エンパワーメント」「パートナーシップ」「ワーク・ライフ・バランス」「ネットワーク」の4つの視点が大事だと話されました。
最後に、小崎さんは「父親の育児は子育て支援のパラダイムシフト。父親が変化することで、社会が変わる『父親支援のドミノ倒し』で、全ての子ども、家庭を支えていくため、支援者と行政の役割を考え、地域や保育関係者、団体など巻き込み、みんなで繋がっていきましょう」と受講者へメッセージを贈られました。
「アバンセ館長コラム」
この講座について田口館長が紹介しています。是非ご覧ください♪
第34号 令和7年2月号「不機嫌は環境破壊」
お知らせ「父親支援マニュアル」
小﨑さんがメンバーを務める「父親の子育て支援研究班」が作成した「父親支援マニュアル」が、
国立成育医療研究センター・研究所のHPで公開されています。
父親支援が多くの自治体・地域に広まることを目指して作成されています。是非ご活用ください↓
https://www.ncchd.go.jp/scholar/research/section/policy/project/2024_manual.html
(令和6年度こども家庭科学研究費補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「父親の子育て支援推進のためのプログラム確立に向けた研究」)
受講者の感想(アンケートより抜粋)
- 様々な視点からの価値観や捉え方を学ぶことができて、これが良い、あれが悪いではない、斬新なアプローチでとっても有意義でした。小﨑先生がおっしゃるように、父親支援からドミノ倒しのように素敵な環境が広がって行ければと思うとともに、私も力になっていきたいと思います。
- 「子どもの横にいる大人がご機嫌であることが大事、不機嫌は環境破壊」の言葉が印象的でした。社会が変われば、父親も変化しやすいと感じた。自分が子育てする時に聞きたい内容だった。
- 時代、社会、文化を見た時、その時々の育児法を悪とせず、悪い所を見直し、良い所は残し次世代にとってのよりよい育児はどういうものか、考えさせられました。男性の育児に関しての話は、あまり聞いた事がなかったので先生の一言一言が心に届きました。
- 母親支援の事ばかり考えていたが、父親支援も一緒に組み込むことの大切さを学びました。プレパパ、プレママからの継続的な支援につながる様、私達支援者も考えていかなければならない事を感じさせて頂き、ありがとうございました。