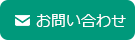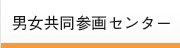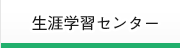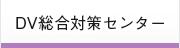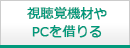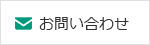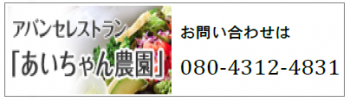令和6年度 家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修) 第2回報告
多様化する社会で大切にしたい親子への支援
リーダー研修は、家庭教育・子育て支援に関わる活動経験年数が3年以上の方を対象とした連続5回講座です。
今年も県内各地の様々なフィールドで家庭教育や子育て支援の活動をされている皆さんが集まりました。
今年の講座では、少し視点を広げて『多様化する社会』をキーワードに、今まであまり取り上げてこなかった『ジェンダー』『父親支援』などもテーマにしています。
様々な経験を重ねてきた支援者の皆さんと「多様化する社会で大切にしたい親子への支援」について、一緒に考えていきました。
R6家庭教育支援者リーダー等養成講座(リーダー研修)チラシ (811KB; PDFファイル)
第2回 親子への支援で大切にしたい「人権」~ジェンダー・多様性の視点から~
【開催日時】12月19日(木)13時30分~16時30分
【講師】田口香津子(アバンセ館長)
講義&ワーク「人権」
講師:田口香津子(アバンセ館長)※手話で「人権」
この日の講師は、前回に引き続きアバンセの田口館長です。はじめに「人権」の歴史や「子どもの権利条約」ができるまでの世界の動きなどを振り返りました。
「子どもの権利条約」は全54条あるそうですが、日本ユニセフ協会では具体的な子どもの権利を定めた第1~40条を、子どもにわかりやすい抄訳として公開しています。その中でも第2・3・6・12条をピックアップした「子どもの権利条約4つの原則」は、日本で2023年に施行された「こども基本法」の理念の礎となっているそうです。
その後、やさしい日本語に訳された「わかりやすい谷川俊太郎訳 世界人権宣言」(アムネスティインターナショナル日本)」をみんなで読み解いていきました。この世界人権宣言は第二次世界大戦の反省からつくられたもので「あらゆる人が誰にも侵されることのない人間としての権利を生まれながらに持っている」と表明したものです。
今回のテーマは「親子への支援で大切にしたい『人権』」ということで、子どもだけでなく「大人」、全ての人に人権があることを改めて学びました。
講義「多様性とジェンダー」
最近よく耳にする「DEI」。これはダイバーシティ(多様性)、エクイティ(公平性)、インクルージョン(包括性)の頭文字をとっていて、わかりやすくいうと「多様な人が存在する社会で、それぞれに合った対応をすることで、それぞれがいきいきと暮らしていけたらいいね」という意味です。
この中の「公平性」と「平等」について事例を交え考えました。みんなに一律にサポートを行うのが「形式的平等」。一方、それぞれの人が抱えている状況に合わせて必要なサポートを行うのが「実質的平等(公平=エクイティ)」で、この「エクイティ」がこの多様化する社会で必要な概念だと述べられました。
次に、支援するうえで知っておきたい「力関係の構図」についてもお話がありました。力がある側は加害者になりやすく、力がない側は被害者になりやすい、また第三者も力がある側に傾きがちになってしまう構図があること、また私たちも状況によって、どの立場にもなりえることを自覚したうえで支援することが大切だと話されました。
また、「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」にも触れられ、その中でも「ステレオタイプ」と「慈悲的差別」の2つを取り上げられました。
「ステレオタイプ」は「男だから~、外国人はみんな~」など属性ごとの特徴を決めつけてしまうことです。
「慈悲的差別」は「大変だから無理して参加しなくていいよ」など好意的だけど、本人の意向を無視した思い込みを優しさと勘違いすることです。支援者は良かれと思って行っていても、結果的に相手の可能性を摘んでしまうことにつながる危険性を指摘し、支援は相手の自己決定を尊重することが大事だと説かれました。
事例検討(グループワーク)
事例(1)「Aさんの子育て」
Aさんの置かれている状況の説明があり、どんな支援が必要なのかをみんなで考えました。説明ではAさんが母親なのか父親なのかには触れられていません。受講者はどちらを想定して考えるかによって印象が変わってくることを体感しました。これが、講義で出てきた「アンコンシャスバイアス」です。このバイアスによって必要な支援を見落としていないかを考えるきっかけにしてほしいと話されました。
事例(2)多様性を考える事例「(仮)田口家の風景」
父親(兼業農家)、母親(ミャンマー人、介護職)、長男(8歳)の家族の状況の説明があり、受講者は限られた情報から家族3人のそれぞれの立場でそれぞれの言い分や背景、事情を推測していきました。推測したことが事実かどうか確かめることも踏まえた上で、最後は「田口家にできること」をいろんな支援者の立場に置き換えて、みんなで考えました。
今日の学びの共有 ~まとめと感想~
最後に、今日の講座の学びを受講者全員が発表し、共有しました。
田口館長は今日の講座を振り返り、「支援をしていく中で、目の前の一人一人の状況に関心を寄せること、寄り添い続けること、傾聴、選択肢の提供・自己決定の尊重を大切にしてほしい。人権が守られていない現実が多くあるけれど、困った時、悩んだ時に心の中に『人権』という北極星を持ち羅針盤にしてほしい」と、受講者へメッセージを贈られました。
受講者の感想(アンケートより抜粋)
- 子どもの人権、大人にも人権、すべての人に人権があることや、自分の中に思い込みがとてもある事に気がつき反省。自分の思い込みが少しずつなくなる事を目標に仕事をしていきたい。
- 日頃、業務の中でも、国籍、年齢、ジェンダーなど様々な立場や状況の来館者の方と関わることがあり「多様性」と思いながらも、「一体多様性って?」「こんな時どうしたらいいんだろう」「何て言えば良かったのかな」と感じることが多々ありました。そんな中で今日の人権や先入観の話を聞けて良かったです。子どもたち一人一人も、大人の方一人一人も大切に関わっていきたいと思いました。
- 日々見落とされがちな「人権」。すべての人にあたり前にありすぎるので、フォーカスされないが、こんなに奥深く、大切なことなんだと感じました。
- 子どもが幸せな人生を歩めるよう支援に力を入れたいと感じました。子どもの人権は0才からある。年齢は関係ないと思いました。気付かせて頂きありがとうございました。