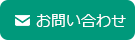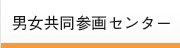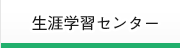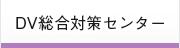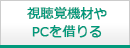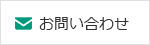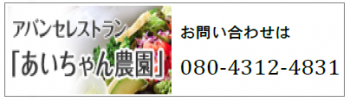令和6年度 学生への意識啓発事業を開催しました
男性保育士からのメッセージ ~社会の中にある男女共同参画を考える~
今年度の学生への意識啓発事業は、佐賀女子短期大学との共催で開催しました。
今回は、社会の変化や価値観が多様化する時代における就職、さらにその人生を描くライフデザインを考えるとともに、固定的性別役割分業やアンコンシャス・バイアスについて学びました。
講師には大阪教育大学の教授で保育学が専門の小崎恭弘(こざきやすひろ)さんに、リモートにて講演いただきました。
講演でお話いただいた内容を一部ご紹介します。
「保母」から「保育士」へ
1977年、男性に「保母」の資格取得が認められるようになるまでは、男性が保育を専門職とすることができませんでした。資格取得が認められてからも名称は「保母」、特定の性差を表すもののままでした。
そんな中で、当時「保母」として働いていた男性たちから、“特定の性を規定する職業の名称は、いろいろな意味の可能性を狭めてしまうのではないか”との声があがり、1999年に「保母」から男女同一資格の「保育士」へと変更されました。この名称は、性別に関わらず、多くの人が関わっていける職業であるということを表しています。
講演では、小崎さんが実際に保育士として勤務されていた時の名刺や辞令書がスクリーンに投影され、肩書きが「保母」と記載されていたことを見せていただきました。
男性保育士の意義
日本の保育における考え方の中で大切にされているのが「環境による保育」という考え方です。保育は子どもにとって豊かな環境を与えていくことが大事であり、その中で男性保育士は大きな「人的環境」です。育児や子育てに積極的な男性がマイノリティである日本において、男性保育士は男性が子育てができるということのひとつのモデルとなります。また、男女が共に子どもを育てるということのモデルになります。
様々な価値観や関わりなどの多様性が必要であり、保育の現場には男性もいれば女性もいる、若い人もいれば年配の人もいる、音楽が好きな人がいれば体操が好きな人もいる、そういった「人的“多様性”の環境」の中で子どもたちはいろいろな関わりやふれあいをしていきます。
日本には従来、男性は仕事、女性は子育て・家事というように性別によって役割を分けられていました。このようなことを固定的性別役割分業といい、これが有効に働いていた時代や社会がありました。しかし今は個人の価値観や生き方の多様性を尊重する考えへと変化しています。女性だから保育士になれるというわけではありません。また、男性保育士にしかできないことというのもありません。保育は子どもの命を預かる専門性の高い職業であり、そこでの性別はひとつの個性・特徴であり、前提条件ではありません。性によって分かれていくのはそれだけ可能性を狭めていってしまうということです。
「モデルなき時代を生きていく私たち」にとっての男女共同参画という考え方
講師の小崎さんが集められたデータでは、今の学生の理想としている生き方は40年前のモデル(親モデル)とのことです。親しか見ていないと、今の時代の生き方や幸せが分からないと述べられました。
「価値観が多様化し、大きく変化する時代を生きていく私たちには、ロールモデルが存在しません。新しい自分モデルを考えてかなければなりません。多様性の時代では男女共同参画という考え方は大きな武器になります。“男だから”“女だから”で価値判断をするのではなく、多様な生き方や選択をできる社会をつくるモデルとなっていってほしいと思います。」と述べられました。
今回はオンライン講演という形式でしたが、講師の小崎さんは背景を佐賀にちなんでバルーンの画像にされたり、画面越しに学生に質問をされたり、学生の反応を見ながら進められ、和やかな雰囲気の講演となりました。
将来保育士や学校への就職を目指す学生にとって、講師の小崎さんの保育士としての経験談を導入に女性の働き方や男女共同参画について展開された講演は、大変参考になった様子でした。
学生の感想(一部抜粋)
講座後のアンケートにも様々な感想が寄せられました。その一部をご紹介します。
・男女の差別や男性の視点の話を聞くことができたのはとても自分の為になりました。
・女性が働いてる職業が1割以下の職業が多くて驚きました。
・生き方や仕事を性別によって制限することは良くないことだと思いました。男女が平等に仕事や子育てをすることが大切だと思いました。
・育休や結婚、出産について、現状がよくわかりました。これからの生き方について改めて考えていきたいと思いました。男性らしさ、女性らしさというのを無意識に考えてしまうことには十分に気をつけたいです。
【主催】佐賀県立男女共同参画センター、佐賀女子短期大学
(開催日:令和6年7月4日 会場:佐賀女子短期大学 131教室)