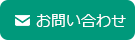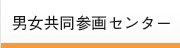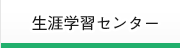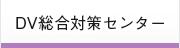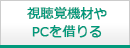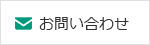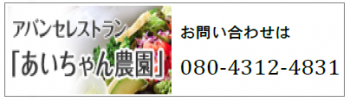令和6年度「女性のためのエンパワーメントセミナー」【第2回】を開催しました
女性を対象に、暮らしのなかで「○○だから」にモヤモヤを感じることや、無意識の思い込みや決めつけに気づき、「わたしらしさ」や「わたしらしい生き方」を探し、「わたしらしさ」を大切にするためのセミナーを開催しました。
(2)カリスマ書店員presents 国際女性デーに読みたいイチオシの本
【講義】矢内 琴江さん(長崎大学ダイバーシティ推進センター 副センター長)
【本の紹介】本間 悠さん(佐賀之書店 店長)
*実施:令和7年3月8日(土)13時30分~15時30分 アバンセ 美術工芸室
第2回目は、今年で50年を迎える「国際女性デー」の3月8日に開催しました。「国際女性デー」に読みたいオススメの本と一緒に、身近なジェンダー課題について学び、「わたしらしさ」や「わたしらしい生き方」を考えました。
前半は、矢内さんから、「ジェンダーやフェミニズムってなんだろう?」と題し、「ジェンダー」や「フェミニズム」の概念や考え方を教えていただきました。
「ジェンダー」は、「文化的・社会的につくられた性別」で、「男らしさ」「女らしさ」のように、男性・女性の身体につけられているイメージのことを指しています。そしてこれまでの社会、特に明治時代以降は、身体的な性別のイメージで、誰かが得するような、また、性別で差があるような制度や仕組みがつくられてきた経緯があることをお話いただきました。身近な社会課題でも、ジェンダーの視点で捉え直していくことが、社会の中の「男らしさ」「女らしさ」の決めつけや性別による偏りに気づくきっかけになることを学びました。
「フェミニズム」は、1880年頃、フランス人の活動家が女性の権利のための闘いを表現する言葉として使い始めたのが起源となり、現在では、女性達が自分達の権利のための言葉として使用するようになったことを学びました。アメリカのフェミニストであるベル・フックスは、自身の著書『フェミニズムはみんなのもの』の中で、「フェミニズムは『性に基づく差別や搾取や抑圧をなくす運動』のこと」と説明していることを紹介していただきました。
この他に、日本の雑誌『青踏』をはじめとした、明治時代以降の「フェミニズム」についてもお話いただき、ジェンダーやセクシュアリティなど性別に関する問題を隣にいる人達と一緒に話して考えていくことが、性別にとらわれない、よりよい社会をつくるきっかけになることを学びました。


後半は、本間さんから、「カリスマ書店員」と呼ばれるようになったきっかけや、ご自身がフェミニズムやジェンダーに関心を持つようになった経緯をお話いただきました。本間さんが、年に1回、その年に読んだ一番おもしろい本を「ほんま大賞」として発表されており、今年(第7回)の受賞作品である『月花美人』(滝沢志郎/著)や第5回の受賞作品である『わたしのペンは鳥の翼~アフガニスタンの女性作家たち~』(古屋美登里/訳)など、本間さんの視点で選書された国内外の6作品を中心に、ご紹介いただきました。
近年、韓国のフェミニズム文学の本が話題になり、日本でも女性を鼓舞するような小説が一気に増えてきていること、直木賞の候補者が全員女性作家になる回もあり、それが社会的ニュースになることも増えてきており、「女性が紡ぐ、女性のための女性文学」のようなものが、最近の流行になっていることなどもお話いただきました。
本間さんからは、「本を読んで勇気をもらい、自分がちょっとでも『おかしい』と感じたことを、『これ、おかしくないですか?』と言えたら、それはもうフェミニズムの一歩なので、みんなで一歩ずつ進んでいけたら」というメッセージをいただきました。

【参加者の声】*アンケートより(一部抜粋)
- 国際女性デーの日に、改めて、ジェンダー、フェミニズムについて考えることができました。私を含めた世間の思い込みって、本当に染みついたものだと感じました。
- 矢内さんのフェミニズムの歴史等が興味深いです。特にフェミニズムという言葉の始まりには、驚愕です。本間さんの本の紹介もとても楽しかった。
- テーマの内容を広く、探っていってあり、良かった。同じグループの参加者と話せて良かった。
- 女性たちの困りごとが多くの本の中に書かれていて、シスターフッド*により勇気をもらえることを知ることができました。
*シスターフッドとは、「女性同士の連帯」や「女性同士の絆」を意味する言葉
(参考)令和6年度「女性のためのエンパワーメントセミナー」チラシ (770KB; PDFファイル)