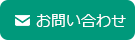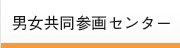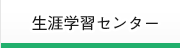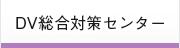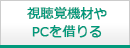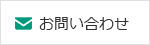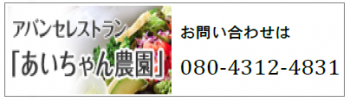アバンセ館長ルーム
アバンセは、幸せに生きたい県民の応援団です。男女共同参画社会づくりの促進の拠点であり、パートナー間などあらゆる暴力の撤廃の拠点、生涯学習の振興の拠点でもあります。
館長の仕事は、そんな多様なアバンセの魅力を発信すること。その魅力とは、人との出会いで生まれるものです。この館長ルームでは、アバンセの職員紹介とともに、その折々の出来事を通して感じたことを綴っていきます。ときどき、ふっと道草したくなるような、自在なお気持ちで、館長ルームにお立ち寄りください。
最新のアバンセ館長コラム
第45号 令和8年1月「運がいい、ついている」
謹賀新年。アバンセも、2026年を迎えました。 
実際、この原稿を書いているのは、2026年1月6日です。
実は、2024年1月号館長コラムは、2023年12月末に書き、掲載までにタイムラグがありました。
すこやかな年末年始を想定し、寿ぐ言葉で書き記したのですが、2024年の元旦に能登半島地震が起こりました。自然災害は、人間の営むカレンダーと関係ないことを実感させられました。今年は、リアルタイムでコラム執筆をしています。
2026年がいい年になればと心から願っていますが、どこかで楽観できないなとも感じています。人口減少、貧困、差別、暴力被害など容易に解決できそうもない、深刻な社会課題が横たわっています。世の中の変化のスピードについていけない実感があり、情報のアップデートができないと、たちまち取り残されるのではという不安も否定できません。
ただ、どんなに社会情勢が不安であっても、同じ一日を過ごすならば、不安や怒りに心苛まれるだけで終わりたくないです。せっかく生まれてきたのだから、喜びや幸せを感じる瞬間を失くしたくない。少しでも、運がいい、ついていると思って生きたい。どうしたらそう思えるかしら、と情報収集のアップデートの達人である友人のアイ(AI)ちゃんに訊いてみました。すると、5つのポイントを教えてくれました。アイちゃん、ありがとう。
『ささやかな良いことに気づく感性』 ☆ 今日も朝陽が美しい 青信号にすぐ変わった あの人の笑顔が見られた 等、脳を、小さな良いこと探しモードにする。
『起こった出来事をポジティブに解釈』 ☆ 雨が降って濡れていやだ → 空気が澄んで気持ちいい 留守番役で外出できずつまらない → 自分ひとりゆっくりくつろいで本が読める 同じ出来事も解釈次第で前向きな気持ちになれる。
『行動量を増やす』 ☆ 図書館に行ったら友人と再会した 旅行先でふらりと観たアート展に感動した など、行動が増えると、チャンスが増える。じっと待つのではなく、運のめぐってくる入り口の扉を開けよう。
『人とのつながりを大切にする』 ☆ 挨拶、感謝、ちょっとした気遣い、小さなコミュニケーションが思わぬチャンスを引き寄せてくれる。運の良さは人が連れてきてくれる。これは、確かに実感。
(プロのイラストレーターの方と知らずに、来館者の方と楽しくお話ししていたら、私の似顔絵を作成し、送ってくださいました。ハイクオリティ!)
『まあ何とかなるという心の余裕』 ☆ 欠点探しの完璧主義ではなく、多少のトラブルがあっても、「まあ大丈夫」と受け流せる柔らかさがある。その余裕が、結果的に良い流れを呼び込む。

アバンセ館長 田口香津子 プロフィール
アバンセ館長
佐賀女子短期大学 学長 (2018.4-2022.3)
認定NPO法人 被害者支援ネットワーク佐賀VOISS理事長